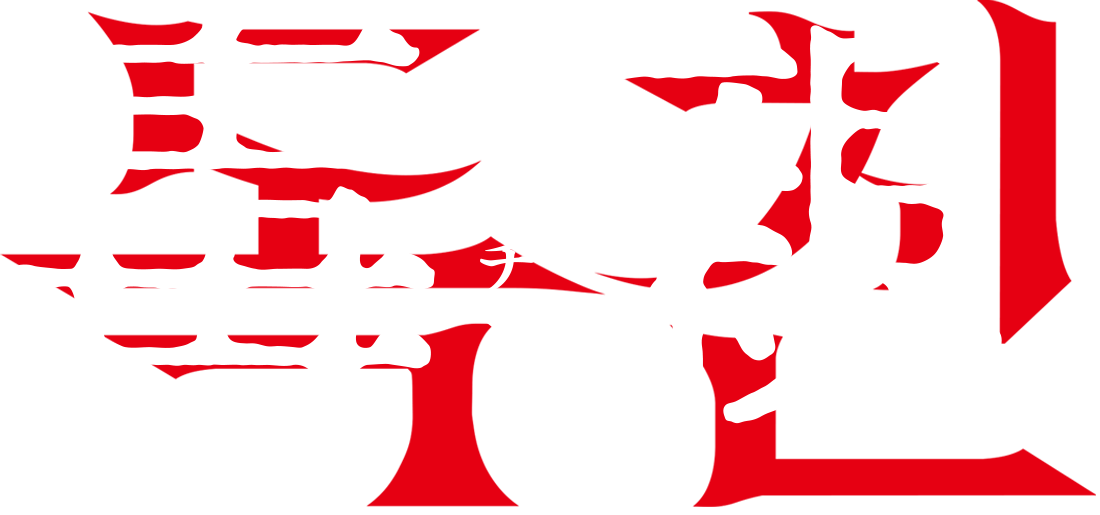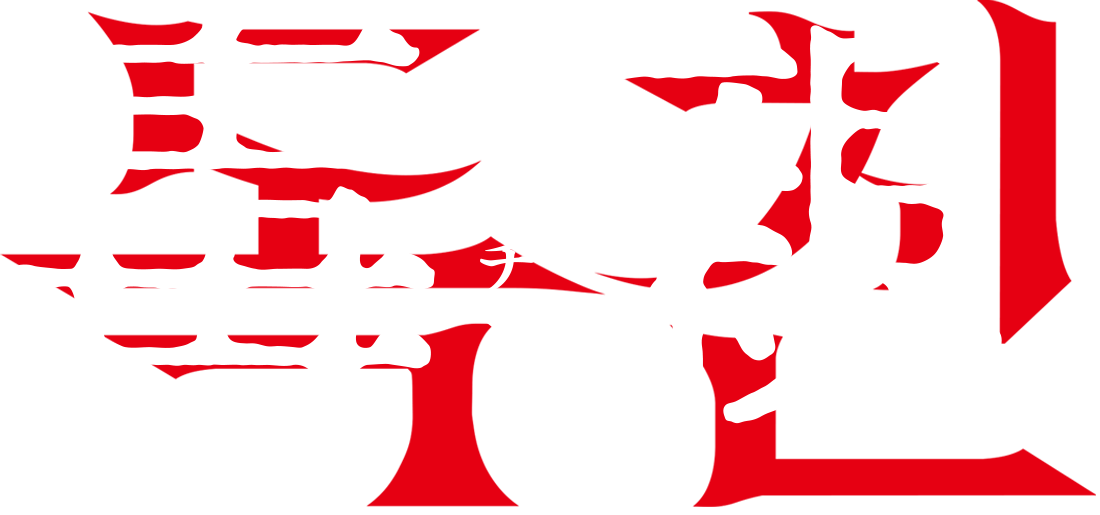日本公開に寄せて
“毒となる親”を題材にしているという点で、この物語は親子の関係を描いていると言えると思いますが、私は最終的にはこの作品を通して、未熟な人間を描こうと考えました。母のヘヨンだけでなく、娘のユリや、友人のイェナ、キボムまで、幼少期のトラウマを思い出しながら生きていたり、あるいはその時代で心の成長が止まっていて、他者へ思いもよらない危害を加えることさえあります。それは決して彼らが悪いからではなく、彼らが受けた傷からすれば、ある意味で当然のことだと、教えてくれる人がいなかったからだと思うのです。特に映画の外の現実に存在する、もう一人のユリ、イェナ、ギボムに「毒親」という概念を伝えたかった…。 毒親に育てられている子供たちが、今、経験している苦痛から、幼少期の影からやがて抜け出し、一歩でも前に進むことができるように。
子どもをどのように愛し、育てるべきか悩んでいる、という視点から、映画の内容に共感する観客もいる一方で、親からのたったそれだけの干渉で自殺までするのかと、ユリに共感できなかった観客もいるようです。私は「毒親」の批評やレビューを全て見た訳ではないので、観客の反応を全て知ることはできませんが、ある上映で会った女性の観客の方は、特に記憶に残っています。彼女が映画を観ている間、家にいる娘のことを思い出してずっと泣いていた姿に、私も涙が出たからです。
韓国で「ドクチン/독친(毒親)」はまだあまり知られていない、馴染みのない漢字です。ハングル文字は表音文字なので、漢字を確認するまではその意味を明確に理解するのが難しいので、映画のタイトルがハングル文字で「ドクチン」と書かれても、すぐにその意味まで理解する人はいませんでした。実際、インターネット上では「読書(독서/トクソ)(친구/チング)」、「ドイツ人(독일인/トギリン)友達(친구/チング)」などの略称で使われることもありました。
特定の国の社会的な問題というよりは、どこの国でも起こりうる親子の問題として捉えて欲しいと思います。人間が誰かを間違った方法で愛することは、私たち全員が経験する可能性があり、今、まさに私の話かもしれない問題だからです。もちろん、このような個人的な状況を、社会的な文脈から完全に切り離すことはできませんが、根本的には私と私の周りの人たち、一人一人の話であるという事実に焦点をあてて作った作品です。
キム・スイン(監督・脚本)